化学療法
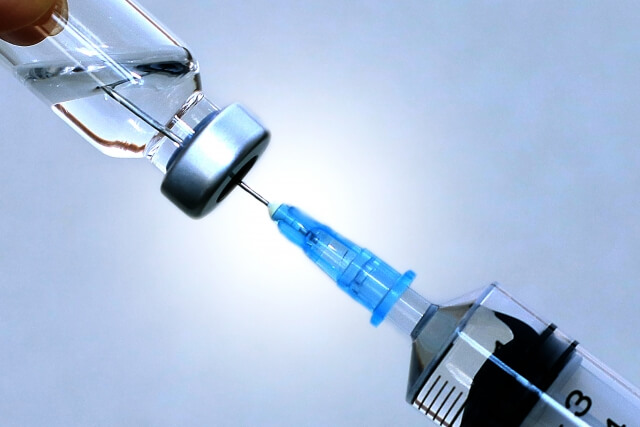
薬物療法(化学療法)は実際のところいいのか悪いのかはわかりません。
私の母は抗がん剤治療で余命3か月と言われていましたが、約2年副作用はありましたが元気で暮らしておりました。
私の知り合いに乳がんの方がいますが、小林麻央さんと同じくらいに乳がんがわかり、抗がん剤等の治療は一切しておりませんし、治療どころかほったらかしです。
なのにものすごく元気で、もしかすると健常者よりも健康かも?と思うくらいです。
身近でそういうのを見ていると抗がん剤は打たないほうがいいのかな?とも思えてきてしまします。
薬物療法とは
薬物療法とは、薬を使う治療のことです。
がんの場合は、抗がん剤、ホルモン剤、免疫賦活剤(めんえきふかつざい:免疫力を高める薬剤)等を使う化学療法が、これに相当します。
症状を和らげるためのいろいろな薬剤、鎮痛剤、制吐剤等も薬物療法の1つです。
ここでは主に、抗がん剤、ホルモン剤を使う化学療法について説明します。
局所療法と全身療法
がんの治療は、「局所療法」と「全身療法」に分けることができます。
局所療法と全身療法の違いは、例えば田んぼの雑草(がん細胞)を刈り取るか、薬をまくかの違いに似ています。
雑草が一部分であれば、正常な作物ごと刈り取ることも可能です(局所療法ー手術など)。
しかし、田んぼのあちこちに雑草が生えてきた場合は、雑草をすべて刈り取ることは不可能なので、田んぼ全体に薬をまき、除草します(全身療法ー薬物療法)。
局所療法
外科療法、放射線療法等があります。
外科療法は、がんを含めて正常細胞の一部を切り取って、がんをなくしてしまう治療法ですから、原発巣(がんが最初にできたところ)にがんがとどまっている場合には完全に治すことができます。
放射線治療は、がんのあるところへ高エネルギーの放射線を照射したり、あるいは小さな放射線源をがんの近くの体内に埋め込んで、がんをなくす方法です。
放射線療法も同様に、原発巣にとどまっているがんの場合には完全に治すことができる場合もあります。
基本的に、外科療法も放射線療法も治療目的で行う場合は、がんが局所(原発巣)にとどまっている場合に適応となります。
それ以外にも、症状緩和の目的で使われる場合もあります。
例えば、骨転移などによって患者さんの疼痛(とうつう)が非常に強い場合には、その部分への放射線照射によって痛みを緩和することができます。
局所への効果をねらって行う薬物療法もあります。
例えば、がんが必要とする栄養を送っている血管(栄養動脈)に、選択的に抗がん剤を注入する「動注療法」も局所療法に当たります。
全身療法
抗がん剤やホルモン剤等の薬剤を、静脈内注射や内服等の方法で投与する薬物療法が主体になります。
がんには、抗がん剤によく反応するタイプのものと、そうでないものがあります。
白血病、睾丸腫瘍等のがんに対しては、薬物療法によって完全に治すことが期待できます。完全に治すことができない場合でも、がんの大きさを小さくすることで、延命効果や痛みなどの症状を和らげることが期待できます。
しかし、薬物療法で使われる抗がん剤の多くは副作用を伴うことが多く、その使用には高度の専門知識が必要です。
がんの化学療法とは
化学療法とは、20世紀の初頭にドイツのエールリッヒ博士がはじめて使った言葉です。
がんの化学療法は、化学物質(抗がん剤)を用いてがん細胞の分裂を抑え、がん細胞を破壊する治療法です。
抗がん剤は、投与後血液中に入り、全身をめぐって体内のがん細胞を攻撃し、破壊します。
どこにがん細胞があってもそれを壊滅させる力を持っているので、全身的な効果があります。
がんは全身病と呼ばれるように、早期にはある部位に限定している局所の病巣が、次第に全身に広がって(転移)、全身的な病気になります。
主ながんの治療法のうち、外科療法と放射線療法は局所的ながんの治療には強力なのですが、放射線を全身に照射することは、副作用が強すぎて不可能ですし、全身に散らばったがん細胞のすべてを手術で取り出すことはできません。
全身病を治すということからすると、化学療法は全身くまなく治療できる点で、より適した治療法と考えられます。
抗がん剤のそれぞれの長所を生かし、いくつかを組み合わせて併用することで、手術の不可能な進行がんも治療できるようになりました。
これからも新薬の開発と併せて、併用療法(抗がん剤を2剤以上組み合わせて行う治療法)の研究が重要になると考えられます。
「抗がん剤」とは
がんに対する薬は現在約100種類近くあり、その中には飲み薬(経口薬)もあれば、注射(注射薬)もあります。また、その投与期間や作用機序もさまざまです。
がんに対する薬のタイプを2つに分類してみると、わかりやすいかもしれません。1つは、それ自身ががんを殺す能力を持ったもので、抗がん剤が相当します。
一方、自分自身はがんを殺すことはできないけれども、がんを殺すものを助ける機能を持つ薬で、免疫賦活剤と呼ばれるものがそれに当たります。
「薬」は、一般に「効果」と「薬物有害反応(副作用)」の2つの作用があります。通常、私たちが薬として使っているものは、効果のほうがずっと強くて、薬物有害反応がほとんどないか、軽度です(例:風邪薬に対する胃もたれ)。
しかし、「抗がん剤」と聞いてすぐ頭に浮かぶのは、「副作用ばかりが強くて全然効果がない」ということかもしれません。
例にあげた風邪薬は、大半の人に非常によく効いて薬物有害反応がほとんどありませんので、効果と薬物有害反応のバランスが取れています。
しかし抗がん剤の場合は、効果と薬物有害反応が同じくらいという場合もありますし、また効果よりも薬物有害反応のほうが多い場合もあります。
したがって、普通の薬と違って非常に使いにくく、治療を受ける側にとっては困った薬であるといえます。
抗がん剤の薬物有害反応が、他の薬に比べて非常に強いことは確かです。悪心(おしん)、嘔吐(おうと)、脱毛、白血球減少、血小板減少、肝機能障害、腎機能障害等の症状が現れます。薬によって薬物有害反応の種類や程度は異なり、また個人差もあります。
これらの薬物有害反応を何とか軽くしようという努力、あるいは一人一人の状態での薬物有害反応を予測し、軽く済ませるための努力が行われていますが、完全になくすことはまだできていません。
なぜ、普通に使われる薬と抗がん剤とではそんなに違うのでしょうか。
薬は一般に、投与量を増やすと効果が出てきます。
もっともっと投与量を増やすと、今度は薬物有害反応が出てきます。
この、効果と薬物有害反応が出現する投与量の幅が非常に広いのが、一般の薬です。
通常量の10倍くらい投与しても、それによって命を落とすことはありません。
これに対して抗がん剤は、効果を表す量と薬物有害反応を出す量がほぼ同じ、あるいは場合によっては、これが逆転している場合さえあります。
すなわち、投与量が少ないところですでに薬物有害反応が出て、さらに投与すればやっと効果が出るといったような場合です。
したがって、抗がん剤で効果を得るためには、薬物有害反応を避けられないことが多いのです。
「この抗がん剤はよく効く」と書いてあれば、おそらく「これでがんが治る」と考えられるかもしれません。
しかし多くの場合、そういうことはありません。
抗がん剤で治療して、画像診断ではがんが非常に小さくなり、よく効いたように感じたとしても、残念ながらまた大きくなってくることがあります。
それでも見た目には著明に効いたようにみえますので、「効いた」といわれるわけです。
例えば肺がんの効果判定では、CTなどによる画像上で、50%以上の縮小を「効いた」と判断します。
もちろん、抗がん剤でがんが完全に治るということもありますが、通常「抗がん剤が効く」という場合、「がんは治らないが寿命が延びる」、あるいは「寿命は延びないけれども、がんが小さくなって苦痛が軽減される」といった効果を表現しているのが現状です。
もちろんそれで満足しているわけではなく、がんが完全に治ることを目指しています。
しかし、難治性のがんの多くでは、効果よりも薬物有害反応の目立つことが少なくありません。
抗がん剤の種類
抗がん剤は作用の仕方や由来等により、「細胞障害性抗がん剤」と「分子標的治療薬」に分類されます。
「細胞障害性抗がん剤」はさらに、代謝拮抗剤(たいしゃきっこうざい)、アルキル化剤、抗がん性抗生物質、微小管阻害薬等に分類されます。アルキル化剤や抗がん性抗生物質はある一定の濃度に達すると、作用時間が短くても確実に効きます。
しかし、正常細胞への攻撃も避けられません。
そこで現在、薬をより効果的にがん病巣に到達させる研究が盛んに行われています。また最近は、がんに特異性の高い標的を探し出し、その標的に効率よく作用する薬(分子標的治療薬)の開発が積極的に行われ、すでに医療の現場で使われはじめています。
より薬物有害反応が少なく、効果の高い薬の開発が期待されています。
代謝拮抗剤
増殖の盛んながん細胞に多く含まれる酵素を利用して、増殖を抑え込もうとする薬です。代謝拮抗剤はプロドラッグといって、本来の働きをする前の化学構造を持った薬として投与されます。
これががん細胞の中にある酵素の働きを受けて活性化され、抗がん剤としての効果を発揮するようにつくられています。
しかし、この酵素は正常細胞にも存在するので、ある程度の薬物有害反応は避けられないことになります。
この薬はがん細胞が分裂するときに効果を発揮するため、個々のがん細胞が分裂するときをねらって、長時間、持続的に薬を投与する必要があります。
アルキル化剤
もともとは、毒ガスの研究から開発された薬です。
遺伝情報の伝達など、生命の本質に重要な役割を果たしているDNAに働く薬です。
DNAは普通、核塩基が対になって2本の鎖状に結合し、それがらせん状にねじれた構造になっています。アルキル化剤は、強力で異常な結合をDNAとの間につくります。
するとDNAの遺伝情報が障害され、またDNAそのものも損傷を受けます。
細胞が分裂してがん細胞が増殖する際には、アルキル化剤が結合した場所でDNAはちぎれ、がん細胞は死滅します。
抗がん性抗生物質
細菌に対してペニシリンといった抗生剤が選択的に効くように、がん細胞に対しても選択的に働く抗生物質があるのでは、という研究のもとに開発されました。
ある種の抗生物質と同じように、土壌に含まれる微生物からつくられたものです。
もともと細菌やカビに効く構造を持った抗生物質の化学構造を変化させたりすることにより、がん細胞を死滅させる効果を発揮するようになったものもあります。
微小管作用薬
細胞の中にあって、細胞の分裂に重要な微小管というものの働きを止めることにより、がん細胞を死滅させます。
微小管に対する作用の違いにより、ビンカアルカロイドとタキサンの2種類の化学物質に分類されます。
また、微小管は神経細胞の働きにも重要な役目を負っているため、これらの抗がん剤によって、手足のしびれなどの神経障害が出ることがあります。
その他
白金製剤:DNAと結合することにより、がん細胞の細胞分裂を阻害します。
トポイソメラーゼ阻害剤:DNAを合成する酵素(トポイソメラーゼ)の働きを阻害することにより、がん細胞の分裂を阻害します。
分子標的治療薬
従来の抗がん剤は、ほぼ偶然に発見された細胞障害作用のある物質の研究によって、開発されてきました。
そのため、それらはがん細胞を殺す能力に重点が置かれてきたため、がん細胞と正常細胞を区別する力が乏しく、多くの薬物有害反応が生じていました。
しかし、近年の分子生物学の急速な進歩により、がん細胞だけが持つ特徴を分子レベルでとらえられるようになりました。それを標的とした薬は分子標的薬と呼ばれ、開発が進んでいます。
白血病、乳がん、肺がん等で、有効な治療手段となりつつあります。
薬物の投与方法
薬物の投与方法には、静脈注射や経口投与等があります。
筋肉注射や胸腔内(きょうくうない)、腹腔内(ふくくうない)、あるいは各種臓器やがんそのものに直接投与する場合もあります。
抗がん剤も上記の方法で投与されますが、溶解性や局所の血管への刺激性等といった薬物の特徴により、投与に工夫が必要なこともあります。
中心静脈という太い静脈に、直接薬物を注入する方法も行われます。
治療効果をあげる工夫として、がん病巣の栄養動脈に抗がん剤を直接注入する「動注療法」が行われることもあります。
栄養動脈は、がんが増殖するのに必要な酸素や栄養を含んだ血液を運んでいます。
この動脈血管に直接抗がん剤を注入する化学療法の一種を、動注療法といいます。
この治療法は局所療法なので、原則として全身に広がったがんには行いません。
しかし全身に広がったがんでも、そのうちの一部が特に生命に影響を及ぼすと判断される場合には、その部位に対し動注療法を行うことがあります。
この療法を行うためには、目的箇所の栄養動脈にカテーテルを挿入する必要があります。臓器固有の太い動脈がある肝臓や腎臓に対して、動注療法が適用されます。
また、上顎(じょうがく)がんなどの頭頸部(とうけいぶ)がん、骨腫瘍、卵巣がん、膀胱(ぼうこう)がん、前立腺がん、膵(すい)がん、さらには進行した乳がん等にもこの動注療法が用いられることがあります。
経口投与は患者さんにとって便利な投与方法ですが、消化管からの吸収量に個人差が大きいため、開発が難しいとされています。
また、飲み忘れといったことも起きやすいため、患者さんの十分な理解が必要になります。
がん治療における薬物療法の目的
がん治療の最大の目的は、患者さんの生命を保つことです。
場合によっては、がんの増殖を遅らせること、がんによる症状から解放すること、全身状態(QOL:クォリティ・オブ・ライフ:生活の質)の改善等を目的とすることがあります。
治療内容は、最善のものが選ばれるようになっています。
どんな治療が最善かは、その方の生活信条や生活習慣により異なります。
がんの治療は、日々進歩しています。
治療方針を決定するため、治療法についての正確な知識が主治医より説明されます。
いろいろな治療法が登場していますが、どの治療法にも適応(有効)と限界があり、すべてに有効という完全な治療法はまだありません。
1つの治療法では完治が望めない場合には、いくつかの治療法を組み合わせ、それぞれの限界を補いあって治療しようという研究が行われています。
このような治療法を、「がんの集学的治療」と呼んでいます。
化学療法で治癒可能ながん
抗がん剤で完治する可能性のある疾患は、急性白血病、悪性リンパ腫、精巣(睾丸)腫瘍、絨毛(じゅうもう)がん等です。
わが国におけるこれらのがんによる死亡者数は、1年間に15,000〜16,000人です。胃がんや肺がんの年間死亡者数は、それぞれ70,000人と50,000人ですから、それらに比べると比較的まれな疾患ということができます。
また、病気の進行を遅らせることができるがんとしては、乳がん、卵巣がん、骨髄腫(こつずいしゅ)、小細胞肺がん、慢性骨髄性白血病、低悪性度リンパ腫等があります。
投与したうちの何%かで効果があり症状が和らぐというのが、前立腺がん、甲状腺がん、骨肉腫、頭頸部がん、子宮がん、肺がん、大腸がん、胃がん、胆道がん等です。効果がほとんど期待できず、がんが小さくなりもしないというがんに、脳腫瘍、黒色腫、腎がん、膵がん、肝がん等があります。
ところで、治療を受ける前に抗がん剤が効くか効かないかを予想できれば理想的です。
例えば感染症に対する抗生物質では、あらかじめその抗生剤が感染症の原因となっている病原菌に効くかどうかを検査したうえで、投与する場合があります。
そのようなことが抗がん剤でできないのかという疑問が、当然出てきます。投与する前に行う「抗がん剤感受性テスト(がん細胞と抗がん剤を接触させ、増殖の抑制をみる検査)」というものがありますが、現在のところこの検査の有効性は不十分で、一般的には用いられていません。
化学療法で治癒が可能ながんと、化学療法の効果の特徴をあげてみましょう。
小児の急性リンパ性白血病
成人の急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病
急性白血病は、化学療法による治癒が期待されている代表的な疾患です。
急性白血病の治療とは、化学療法によって、できるだけ白血病細胞を減少させることです。化学療法により体内の白血病細胞が一定の数以下に減少し、正常な造血能力が回復すると、貧血や白血球減少、血小板減少は解消され、すべての症状も消失します。
この状態を完全寛解といい、そのために行う治療が寛解導入療法です。
しかし、完全寛解の状態になっても白血病細胞は残っているので、寛解後療法、いわゆる「地固め療法」と呼ばれる化学療法を引き続き行い、さらに維持、強化療法を行って、白血病の再発予防、治癒を目指します。
また、白血病の化学療法を行っている間は、病気それ自体および化学療法剤による薬物有害反応のため、出血や感染などの危険な合併症を起こす可能性があります。この合併症を防ぐ治療、つまり支持療法(補助療法)も重要です。
急性骨髄性白血病やリンパ性白血病の中心的抗がん剤は、塩酸ダウノルビシン、塩酸イダルビシン、シタラビン等です。
寛解導入療法では、一般にこれらの薬剤の中から2種類を併用します。地固め療法後、さらに白血病細胞を減少させるために1〜2ヵ月間隔で行われるのが、強化療法です。
寛解導入療法、地固め療法と同等の強さの治療を行います。また、完全寛解後の最強の治療法として、骨髄移植や最近はミニ移植が行われています。
従来の骨髄移植は、正常骨髄が回復できないくらい大量の薬剤投与と強力な放射線療法で、白血病細胞をほとんど消失させた後、白血球型(HLA型)の適合した骨髄提供者の末梢血幹細胞や骨髄液を点滴で移植する治療法です。
ミニ移植では、移植幹細胞の生着を助けるため抗がん剤を用いますが、従来の骨髄移植ほど強力には抗がん剤を使用しません。
移植細胞の免疫により、白血病細胞を攻撃し治療するのが目的です。
急性白血病の治療の場合、出血および感染などの重い合併症を併発する危険が高いので、無菌室や無菌ベッドの使用が必要です。
その中で、抗生物質や輸血等の支持療法が行われます。
急性白血病では、骨髄性でもリンパ性でも完全寛解率は70%以上です。
現在、骨髄性の場合は、完全寛解した30%前後の方は5年以上再発せず治癒していると考えられていて、この成績は向上しています。
悪性リンパ腫
悪性リンパ腫は、ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に分類されています。
非ホジキンリンパ腫は、化学療法と放射線療法で治癒可能になりました。
病理組織学的悪性度、病期(病気の進行度)、全身状態等によって治療法を選択します。多くの場合、抗がん剤の多剤併用化学療法を行います。
抗がん剤は、塩酸ドキソルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン(副腎皮質ホルモン剤)、CD20抗体(リツキシマブ)等を組み合わせて使用します。
強力な治療法ですが、専門病院での治療成績をみると、完全寛解率は50〜80%、5年生存率は40〜60%でかなりの患者さんが治癒する疾患といえます。
ホジキンリンパ腫のI、II期では放射線療法単独、もしくは放射線療法と化学療法との併用が、III、IV期では化学療法が選択されます。
III、IV期症例に対する化学療法による成績は、5年生存率で40〜80%と幅がみられますが、比較的多く治癒します。
精巣(睾丸)腫瘍
成人のがんでは、化学療法が最高の治癒率を示すがんです。
シスプラチンを中心とする多剤併用化学療法で、70%以上にがん細胞の完全な消失が認められ、治癒率も60%以上と小児急性リンパ性白血病に匹敵します。
卵巣がん
シスプラチンを主体とする多剤併用化学療法が、よく用いられます。
化学療法を行った後、2回目、3回目の手術が行われることもあります。40%以上にがん細胞の完全消失が認められます。
絨毛性疾患(女性のがん)
ほぼ100%の治癒率を示します。
メトトレキサートやアクチノマイシンD等の抗がん剤を中心とした化学療法を行い、その後は必要に応じて外科療法を併用します。
以前は子宮摘出が主体でしたが、現在は抗がん剤による化学療法が改善され、治癒率も高くなっています。
化学療法を行った場合の薬物有害反応としては、口内炎、脱毛、悪心(おしん:吐き気)、嘔吐(おうと)、白血球減少等がみられます。
小細胞肺がん(肺がん)
小細胞肺がんでは抗がん剤は有効で、多くの場合がん細胞は縮小し、消失することもあります。
しかし再発する場合も多く、その場合の抗がん剤の投与については、まだ研究途中の段階です。
エトポシド、シスプラチン、カルボプラチン、塩酸イリノテカン等の薬剤が主に使われています。
現在、わが国で広く用いられている組み合わせは、以下のとおりです。
- シスプラチンと塩酸イリノテカンの2剤併用
- PE療法:シスプラチン、エトポシドの2剤併用
これらの併用療法を、3〜4週間隔で4〜6回繰り返し行うのが標準的です。
また、多数の抗がん剤を毎週使用する方法が検討されています。
延命を目的として治療するがん
完全に治すことが期待できない場合でも、化学療法でがんをコントロールしつつ、できる限りQOLの高い日常生活を送りながら、しかも長期に生存することを目標とします。
延命を目的として治療するがんには、以下のようなものがあります。
頭頸部がん
シスプラチンにより、治療成績は飛躍的に向上しました。外科療法や放射線療法の前にシスプラチンを含む多剤併用化学療法を行うことで、治癒の可能性も期待できます。
現在は、シスプラチン+フルオロウラシルが多用されています。
食道がん
肝臓など、食道から離れている遠隔臓器に多発性のがんが転移している場合は、抗がん剤を用いた化学療法が治療の中心となります。
シスプラチンとフルオロウラシルを中心とする抗がん剤の多剤併用化学療法や、放射線療法との合併療法が有効です。
近年は、転移だけでなく、もともと発生した部位では広がっているけれど、まだその部位にとどまっているがんに対しても化学療法と放射線療法の併用を行います。
また、普通の手術後の治療法として、放射線の術後照射と併用しても行います。
非小細胞肺がん(肺がん)
小細胞肺がんと比較すると効果は低いのですが、シスプラチンを中心とする多剤併用化学療法で、以前よりよい治療成績が得られています。
外科療法や放射線療法等の局所療法とは異なり、化学療法は抗がん剤による全身治療法なので、がんが転移するなど進行した場合では化学療法が治療の主体となります。
現在、広く使用されている抗がん剤には、シスプラチン、カルボプラチン等の白金製剤を軸に、酒石酸ビノレルビン、塩酸イリノテカン、パクリタキセル、ドセタキセル、塩酸ゲムシタビン等を組み合わせる2剤併用療法が主流です。副作用や効果を考慮して、組み合わせを替えたりします。
延命効果はまだ不十分なので、QOLを十分に考慮して治療を行う必要があります。最近は、分子標的治療薬であるゲフィチニブも使用されるようになりましたが、従来の抗がん剤との組み合わせ方はまだ研究段階です。
乳がん
薬物療法が比較的よく効くがんです。乳がんの薬物療法には、ホルモン剤、抗がん剤、抗体療法があります。
ホルモン療法や抗がん剤は、手術後に用いたときの再発予防効果、再発・転移したがんでの延命効果が証明されています。ホルモン療法は、女性ホルモンの受容体を発現しているがんが対象となります。化学療法としてはアドリアマイシン、シクロホスファミド、パクリタキセル、ドセタキセルなどの注射薬等のほか、フッ化ピリミジン系の内服の抗がん剤(カペシタビンなど)が用いられます。HER2タンパクが過剰に発現している再発・転移性乳がんでは、抗体療法(トラスツズマブ)による延命効果が確認されています。
最近では、しこりの大きい乳がんを対象として、手術の前に抗がん剤投与を行う「術前化学療法」が普及してきました。
胃がん
胃がんでは、手術が不可能な場合や手術の補助手段、手術後の再発防止など、補助的な治療法として用いられています。
フルオロウラシルという抗がん剤が有効で、これを中心とする多くの多剤併用化学療法が行われます。
大腸がん
現在、大腸がんには、抗がん剤がいくつか使用されています。ある程度進行したがんに対して、根治的な手術後、再発を少しでも防止するための補助的手段として使われることがあります。
また、がんが切除されなかった場合や、手術後再発し、再手術では切除できないような病変に対しても、抗がん剤はしばしば使用されます。
フルオロウラシルが有効で、近年、この抗がん剤の奏効率を高める治療の研究が進み、好成績が得られつつあります。
最近、塩酸イリノテカンが有効であることも報告されています。
膵臓がん
重い全身合併症がなく、肝臓、腎臓、骨髄機能に高度な障害がない場合は、化学療法が行われます。
使用される抗がん剤には、ゲムシタビン、フルオロウラシル等がありますが、単独では薬剤の効果が十分でないことが多く、効果を高めるためさまざまな努力がなされています。
膀胱がん
肺や骨、リンパ節など他の臓器への転移がある場合には、シスプラチンを中心とした抗がん剤を使用して、全身化学療法を行います。
多種類の薬剤を併用して行いますが、薬物有害反応がかなり強くみられます。奏効率は、60〜70%といわれています。
子宮がん(子宮頸がんと子宮体がん)
手術後は、抗がん剤のシスプラチンを主体とする多剤併用化学療法でがん細胞の完全消失が認められ、長期に生存している患者さんも増えています。
子宮体がんでは、大量の黄体ホルモンによる内分泌療法が行われる場合が多いようです。
外陰がん
腟がん
外科療法や放射線療法等を主体とした治療を行いますが、抗がん剤などによる化学療法を併用することがあります。
悪性黒色腫(皮膚)
ある程度進行していたら、化学療法を併用します。
軟部腫瘍(成人)(小児)
新薬の誕生までの道のり
最初の抗がん剤の発見以来、約30年の間に100種以上の新薬が開発され、現在、治療に用いられています。
抗がん剤は、植物の成分、細菌の培養液など多くの資源から探索されます。あるいは、人工的に合成する場合もあります。
新しい抗がん剤の候補が発見されると、ヒトの培養がん細胞やヒトのがん細胞を植えつけた動物に対しての有効性が研究され、次にその薬物有害反応が研究されます。
がんに対する効果と、ヒトが耐えられるかどうか、その薬物有害反応はどういう種類でどの程度か等が判断された後に、実際のがん治療における有効性を知るために、臨床の研究へとステップアップします。
ヒトでの臨床研究では、まず、薬物有害反応、血中濃度、有効性等の研究(第I相研究)が行われます。このときに安全な投与量が決定されます。
次に、この安全な投与量を用いて、薬の有効性と有害事象が研究されます(第II相研究)。以上の結果から、市販する価値を認められた薬のみが、広く治療に用いられます。
一般に、新薬の発見から市販までに10年以上かかるといわれるほど、長い慎重な研究を重ねて新しい抗がん剤が誕生します。
しかし、それでは有効な抗がん剤の恩恵を受けられない方も多いので、よく効く抗がん剤はできるだけ早く使えるようにしようという努力がなされています。
抗がん剤による薬物有害反応について
抗がん剤には、がん細胞を死滅させるとともに、正常な細胞も傷害させてしまうという作用(薬物有害反応)があります。
理想的な抗がん剤は、がん細胞だけに作用して正常な組織には作用しないという薬ですが、残念ながらそのような薬は現在のところ存在しません。
もちろん、分子標的薬といったがんにのみ作用する抗がん剤の開発、あるいは投与の工夫により、なるべくがんへの選択性を高めるための研究が行われていますが、薬物有害反応をゼロにすることはできていません。
抗がん剤の薬物有害反応はさまざまですが、正しく使えば多くの場合は使用を中止すれば治ります(可逆性)ので、がんの治療は可能です。
薬物有害反応を薬により軽減させることも、薬物療法の大きな役割です。
治療を受ける方が薬物有害反応に十分耐えることができ、そして十分効果的にがん細胞を破壊できる抗がん剤が、実際の治療に使用されています。
近年では、薬物有害反応の異なる複数の抗がん剤を同時に用いて薬物有害反応を分散させ、がんに対する効果も増強させる多剤併用化学療法が行われています。
特徴の異なる薬剤を組み合わせることによってすべての薬物有害反応が軽く済み、軽い薬物有害反応なら薬物有害反応防止剤で克服できるということです。
がんの化学療法を安全に行うためには、抗がん剤の効果と薬物有害反応を熟知している専門医による治療が必要です。
主治医は、通常どのような薬をどのように内服、または静脈注射するかとともに、その治療を受けた場合の効果と、どのような薬物有害反応が出るかを詳しく説明します。
そのときわからないことがあれば必ず質問するなどして、よく理解したうえで治療を受けることが大切です。薬物有害反応をコントロールすることが、抗がん剤による治療にとって重要です。
病状をよく知り、その治療の必要性をよく理解することは、薬物有害反応に対する心構えにもなります。以下に主な薬物有害反応について述べます。
血液毒性ー骨髄抑制
抗がん剤の多くは増殖が盛んな細胞に作用するため、骨髄細胞や毛根といった正常細胞もダメージを受けやすくなります。
骨髄細胞(幹細胞)は血液中の細胞(白血球、赤血球、血小板)のもととなる細胞のため、これらがダメージを受けることにより、血液中の白血球、赤血球、血小板の減少が起こります。
これらの細胞は、免疫、酸素運搬、血液凝固といった大切な役割を持っているので、減少の度合いが強いと命にかかわりかねません。
そのため抗がん剤を投与するときは、頻回に採血をし、毒性をモニターすることが大切となります。
白血球の減少と発熱
ほとんどすべての抗がん剤に白血球減少がみられるため、抗がん剤の投与量が規制されます。白血球減少は、最も高頻度に現れる薬物有害反応といえます。
白血球が減少する時期は抗がん剤の種類によって違いますが、3〜4週間の間隔で注射をする場合、多くは10〜14日後に最も減少します。
減少する程度は個人差があります。そして白血球数が2,000/μl以下になって免疫力が低下し、発熱、感染症(肺炎など)の可能性があると判断した場合には抗生物質を投与することがあります。
白血球減少に対して、抗がん剤を投与した後に顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)を皮下注射、または静脈注射して白血球減少を予防したり、回復を早めることがあります。
血小板の減少と出血傾向
血小板は出血を止める働きがあるため、血小板が減少すると出血しやすくなり、皮下に出血斑ができたり、歯を磨いたときに出血するようになります。
さらに血小板減少が重症化すると、脳出血や消化管出血のおそれが強くなるので、入院をして血小板輸血をしなければならない場合もあります。
血色素の減少と貧血
赤血球は白血球に比べて寿命が長いため、抗がん剤により高度の貧血を起こすことはまれですが、軽度の貧血はよく起こります。
血色素が7〜8g/dlになるとめまいなどの症状が出ることもあります。
抗がん剤の投与によって消化管出血などを起こしやすくなるため、出血による貧血も起きやすくなります。
短期間で貧血を改善する薬はまだないので、貧血が高度の場合は、輸血による治療を行います。
吐き気や嘔吐
抗がん剤による吐き気は、投与1〜2時間後から起きる早期のものと、1〜2日後から出てくる遅発性のものがあります。
ともに個人差が大きく、精神的な影響も関係するせいか、女性に多くみられます。
多くの抗がん剤で共通する薬物有害反応ですが、その機序は研究段階です。
早期の吐き気は24時間以内に治まることが多いですが、シスプラチンなどの薬剤は24時間を超えても持続します。
患者さんにとってはつらい薬物有害反応のため、抗がん剤の治療をするときには、吐き気が起きる前に制吐剤を抗がん剤と一緒に投与します。
メトクロプラミド、ステロイドホルモン、塩酸グラニセトロン、塩酸オンダンセトロン等が使用され、昔に比べると吐き気はかなり薬でコントロールできるようになりました。
遅発性の吐き気は出現した場合、早期の吐き気に比べて、薬でのコントロールが難しいとされています。
しびれ感
微小管作用薬などの治療では、指先や足先からはじまるしびれ感が出ることがあります。
進行すると手足の感覚がなくなり、食事中にはしを落とすような症状が出ることがあります。
指先の運動など血行をよくすることが大切ですが、回復しづらい症状のため、悪化させないためには抗がん剤の投与を中止する必要があります。
ビタミン剤を使うことがありますが、効果は不十分です。
しびれ感など末梢神経障害に対する新薬が開発中です。
ホルモン療法とは
特定のホルモンを分泌している部分を手術で取り除いたり、経口や注射によってそのホルモンと反対の作用をするホルモンを投与して、がん細胞の発育を阻止する治療法が行われます。
この治療法をホルモン療法(内分泌療法)といい、がん細胞を殺すのではなく、がんの発育を阻止してコントロールするのが特徴です。ホルモン療法は長期間の治療になります。
治療の対象となる主ながんは、乳がん、子宮体がん、前立腺がん、甲状腺がん、腎がん等です。
乳がん
乳がんでは、エストロゲンという女性ホルモンががん細胞の発育を促進しています。そこで、女性ホルモンの主な供給源である卵巣を取り除く手術を行います。
薬剤を用いる方法では、女性ホルモンとは反対の作用をするホルモン剤(男性ホルモン)を経口、あるいは注射によって投与します。
子宮体がん
ほとんどが子宮内膜がんで、メドロキシプロゲステロンアセテートなどのホルモン剤と抗がん剤を併用して治療します。
初期や再発したがんに用います。
特に初期のがんでは、高い効果が認められています。
前立腺がん
前立腺はがん化しても、男性ホルモンに強く支配されています。男性ホルモンの供給源である睾丸(精巣)を取り除く手術を行う治療法もありますが、高齢者などでさまざまな合併症がある場合には、化学療法あるいはホルモン療法が主な治療の手段となります。
睾丸からのテストステロンの分泌を抑える薬剤や、男性ホルモンの働きを抑える抗男性ホルモン剤、男性ホルモンと拮抗する女性ホルモン(エストロゲン)剤等を投与し、抗男性ホルモン剤については新しい薬が検討されています。
これらの治療の薬物有害反応としてインポテンツになったり、乳房が女性のように黒ずんで大きくなったり、痛んだりすることがあります。
さらに、女性ホルモン剤は心臓や血管にも影響を与えます。
ホルモン療法であまり効果がみられないケースや、最初は有効でも期間がたつと効果がなくなってくる場合が10%くらいあります。
このような場合には抗がん剤による化学療法が行われますが、最初からホルモン療法との併用が行われることもあります。
がんの痛みに対する薬物療法
がんがおそろしい病気と考えられてきた理由の1つに、がん性疼痛と呼ばれる強い痛みに長い間苦しみながら死ぬのだと思われていることがあげられるでしょう。
実際、がんの痛みをとる治療は、今まで積極的に行われてはいませんでした。
がんの進行とともに痛みが起こることは多くなりますが、痛みを経験するのは70%の方です。末期になっても、30%の方には痛みは起こりません。
現在では、痛みに関する医療技術が開発され、がんの疼痛はコントロールできるようになってきました。
がんの痛みには鎮痛薬が最も有効です。
危険な作用や薬物依存のイメージで敬遠されていたモルヒネは、安全に使う方法が開発され、痛みの除去に最も有効な薬であると、国際的に重要性が認められています。
痛みの強さの程度により、使用する鎮痛薬は異なります。程度の軽い痛みには、非オピオイドと呼ばれる鎮痛薬を使います。
これは、痛みのある部位に作用して痛みを和らげる鎮痛薬の総称で、アスピリンや非ステロイド性消炎鎮痛薬と呼ばれている薬です。
非オピオイド系鎮痛剤でコントロール不良の痛みやもっと強い痛みには、オピオイド鎮痛薬を使います。
脊髄や脳の中の痛みを伝える神経組織にオピオイド受容体と呼ばれるものがあり、これに作用して痛みを止める薬の総称がオピオイドです。
オピオイドでも、作用の強さから弱オピオイドと強オピオイドの2つに分けられています。弱オピオイドにはコデインやブプレノルフィンがあり、強オピオイドの代表はモルヒネです。
このように分類された鎮痛薬を痛みの程度に応じて選択して使用することにより、実際に痛みの9割以上を除去できます。
痛みに対する治療の最終目標は、痛みが消え、それによってQOLが向上することです。





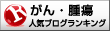


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません